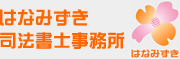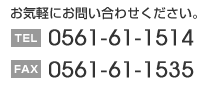12月 18 2014
時効の期間が経過した分も絶対に回収できないわけではありません。
個人間の金銭トラブルであれば通常は10年,売掛金や賃料などは通常は5年,診療報酬だと3年が経過すると消滅時効により債権は消滅してしまい,相手に請求することができなくなります。
ただ,正確に言えば,消滅時効によって債権が消滅するためには,
①時効期間(上記の10年や5年など)が経過すること
②債務者の時効の援用(民法145条)
の2つが必要です。
したがって,時効期間が経過していたとしても,債務者から時効の援用がされていない以上は,とりあえず請求することは可能です。
実は,先日も未払いの賃料について,10年以上延滞されている賃料の回収手続を行いましたが,10年分全額を回収しました。
もし,債務者から時効の援用がされた場合は5年以上前の分は時効によって消滅してしまうため,残りの5年分しか請求することはできませんが,債務者側から時効の援用の意思表示がありませんでしたので,考えて方によっては5年分得したとも言えます(ただ,本来支払ってもらうべきお金をもらっただけなので,得したという表現はおかしいかもしれません)。
もっとも,債務者を騙して回収することはできませんので,時効についての質問があった場合は,弁護士や司法書士に相談に行くように回答することになります(基本的にこちらから時効である旨を伝えることはありません)し,明確に時効の主張をされた場合は,時効中断事由が無い限り認めるしかないと思います。
また,時効期間経過後の債権の請求をする場合,個人間のトラブルではあまり関係ありませんが,売掛金や診療報酬等については,レピュテーションリスクも検討しなければなりません。このレピュテーションリスクというのは,「評判リスク」,「風評リスク」と呼ばれるもので,合法・違法という観点ではなく,とある行為を行うことによって生じるマイナス要素の風評が起きるリスクです。
つまり,本来であれば時効期間が経過している場合は,債務者の時効の援用があればすぐに消えてしまうような債権であるため,「あの会社は,時効になってるような債権まで回収するらしいよ・・・」という評判が立ってしまうリスクです。したがって,時効になっていたとしても援用が無ければ請求できますが,何でも請求した方が良いかというとそうではないと思います。
ということで,上記の時効完成後の債権を回収したというのはかなり特殊な事例ですので,やはり時効期間が経過している債権についての回収は難しいと考えていただいた方が良いかと思います。
と言いつつも,上記の事件の後にも7年程度延滞していた債権を最近も回収しました・・・。