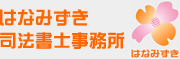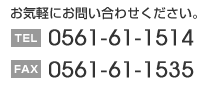6月 06 2016
養育費不払い,口座を裁判所が特定
先日,このような記事がありました。
→横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定(YOMIURI ONLINE 2016年06月04日 07時06分)
以下,上記の記事について引用いたします。
強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。
以上で引用終わり
上記の記事を踏まえて,今回は差し押さえについてまとめてみたいと思います。
差押えについて
養育費に限らず,相手の財産を差し押さえるためには,いろいろな書類や情報が必要となりますが,そのうち重要なものについて記載いたします。
(1)債務名義
債務名義とは,そのほとんどは裁判所が発行する書類で,公的に権利があることを認めている書面です。一番有名なのは「被告は原告に対して100万円を支払え」というような判決の正本になります。判決以外だと,裁判上の和解をした時の和解調書というものも多くあります。また,裁判所が作った書類ではありませんが,執行認諾文言付の公正証書も債務名義となります。
養育費の支払ということは必ず離婚が絡んできますので,債務名義として多いのは離婚調停を行ったときの調停調書が債務名義になることが多いでしょうし,裁判までいっていれば離婚訴訟の判決正本ということもあると思います。また,協議離婚をする際に作成した公正証書ということも多いでしょう。
なお,債務名義は裁判所または公証人が関与したもの以外はありえませんので,当事者が作った「離婚協議書」などでは差し押さえはできません。したがって,離婚協議書しかお手元にない場合に差し押さえまで進もうとなると,離婚協議書を相手方の協力を得て公正証書にするか,養育費請求の調停を申し立てて債務名義を作ることになります。もちろん,差し押さえなどせずに,調停などで合意した養育費を支払ってくれれば問題ないんですけどね・・・。
(2)相手方の財産に関する情報
相手方の財産を差し押さえる場合,その財産は債権者(財産を差し押さえる側)が自ら見つけ出して特定する必要があります。
勤務先の給料を差し押さえる場合は,どの会社にお勤めなのかを探し出さなければなりません。この点,正社員であればまったく問題ないのですが,派遣社員だと実際に働いているところから給料をもらっていないこともありますので,空振りに終わってしまうこともあります。
また,不動産であれば番地等まで調べる必要がありますし,預金口座であれば銀行名と支店名までは特定する必要があります。
上記の読売新聞の記事は,まさにこの部分であり,裁判所が債務者の預金口座を特定してくれるというものです。一般論として,相手がどの金融機関に口座を持っているかを調べることは困難であるため,その意味ではこの制度は役に立つと思います。ただ,実効性があるかどうかはかなり微妙だと思います。
というのは,勘違いをされていらっしゃる方が多いのですが,預金の差し押さえというのは,あくまで差し押さえた瞬間に口座に入っている預金を差し押さえることができるだけであって,以降,その口座に入ってくる預金のすべてを差し押さえることができるわけではありません。
例えば,A銀行が債務者の給与振込口座になっており,給与が毎月25日だとします。もし,25日に給料がすべて口座に入り,全額引き出され,翌26日に差し押さえの書類が金融機関に届いた場合,空になった口座を差し押さえたことになりますので残念ながらお金は回収できません。また,あくまでその26日の差し押さえしか効力がないため,翌月の給与が振り込まれてもその分から回収することはできません。
ですので,このような方法で現実的に回収できるのは,定期預金など,ちゃんとした資産がありながら不払いをしているような場合であり,財産として預金を持っていないような人であれば口座の特定ができたとしても現実的には回収できません。そして,養育費の不払いとなる原因の多くが,「そもそもお金がない」という理由ですので,上記のとおり,実効性があるかどうかは微妙だと思います。
給与差し押さえの例外
上記の例だと,A銀行に給与が支払われる前に,そもそも給与自体を差し押さえてしまえば回収できることになります。しかも,預金と異なり給与の差し押さえは全額回収しきるまで効力が及ぶため,債務者が勤務先を退職しない限り,ずっと差し押さえの効力が及びます。ただ,給料の差し押さえには大きな問題があります。それが25%基準です。
いわゆるサラリーマンの方にとって,給与というのは生活していくうえで一番大事なものです。確かに支払いをしない債務者も悪いのですが,給与を全額取上げてしまうと生活ができなくなってしまいます。そこで,法律では,社会保険料や税金などを控除したいわゆる手取り給与のうち1/4(25%)までしか差し押さえができないことになっています(民事執行法152条1項)。ですので,債務者の給与次第ではありますが,多くのケースで毎月数万円ずつしか回収できませんので,かなりの時間がかかることになります。
ところがところが,これにもいくつか例外があります。
①手取りが33万円を超える場合は全額差し押さえ可能
33万円あれば十分生活ができるでしょう,ということで33万円を超える分については全額差し押さえが可能です。例えば,手取りが50万円の場合は17万円を差し押さえることができ,もし手取りが100万円であれば67万円を差し押さえることができます。
②役員報酬は全額差し押さえ可能
過去の事例でも記載しておりますが,給与と役員報酬は別に考えられており,取締役や監査役など,会社の役員としての報酬は全額差し押さえることができることになっています。役員報酬で生活している人も多数いるので全額差し押さえられた人は生活できなくなってしまうのではないかと思いますが,法律的には全額差し押さえ可能となっております。
③養育費や婚姻費用などの特例
上記2つは一般的な差し押さえの例外ですが,養育費など扶養義務に関する債権については,例外的に1/2を差し押さえて良いことになっています(民事執行法152条3項)。
当事務所が業務として養育費関連のご依頼をお受けすることはあまりありませんが,友人・知人からはよく質問を受ける分野です。当事務所でも強制執行の手続きなどでお手伝いすることができる場合もありますし,専門の弁護士さんを紹介させていただくこともできますので,お気軽にご相談いただければと思います。