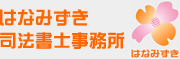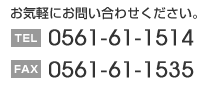2月 20 2024
ご相談いただいてご依頼いただく割合
日々たくさんのご相談をお受けしておりますが、実際にご依頼いただく割合は決して多くありません。正確な統計ではなく、あくまで感覚的な割合ですが恐らく2~3割程度だと思います。
その理由としては、ご相談をお受けした時点で回収の見込みがかなり低いケースが多く、余程の理由が無い限りご依頼いただくメリットが無いと説明させていただいているためです。
以下、ご相談いただいた時点で回収の見込みがかなり低いケースについてまとめてみたいと思います。
第1 回収することが極めて難しい場合
1 SNSでのやり取りのみで相手が誰だか分からない
近年、ネット上でのやり取りのみで金銭の貸し借りをされる方が多くなっているように思います。X(旧ツイッター)やインスタグラムなどのSNSで知り合い、SNS上だけのやり取りでお金(電子マネー)の貸し借りを行うというケースもあります。この場合、相手のアカウントは特定できていたとしても生身の人間としては誰かが分からないため、回収の見込みというよりも誰に請求して良いか分からず、そもそも手続を開始することができません。
なお、近年良く見かける情報として発信者情報の開示請求がありますが、上記のような場合には開示請求ができません。
開示請求に関する特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第5条に、開示請求のための要件が規定されており、その中に「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたこと」が必要であるとされています。「侵害情報の流通」というのは、名誉棄損等に該当するような投稿や第三者の著作権等を侵害する画像や動画の投稿などになり、あくまでその投稿自体が問題になる場合に限られます。
とすると、金銭の貸し借りの相手方に違法な投稿等が無いようであれば発信者情報の開示請求はできないということになります。
2 会ったことはあるがLINEでのやり取りのみで相手の情報が無い
最近はメールではなくLINEでのやり取りが多くなっており、場合によっては相手方に会ったことはあるが電話番号は知らず、LINEでは繋がっているということが多くあると思います。ただ、LINEだけでは基本的には相手が誰であるかを特定することはできませんので、基本的に手続を開始することができません。
ただし、相手方のLINEIDが分かるようであれば、弁護士会照会を行うことで相手方の電話番号などが特定でき、そこから相手方の情報が得られる場合があります。ただし、弁護士会照会は文字通り弁護士さんでしか使えない制度であるため、当事務所では調査することはできません。
また、LINEによって脅迫等をされた場合には、刑事事件にすることでそこから相手方が誰かが判明することがあります。
なお、上記1と2においても、金融機関での送金にてお金のやり取りをしているようであれば、金融機関に弁護士会照会を行うことで相手方が誰であるかを特定できる場合があります。また、SNSやLINEのみのやり取りであっても、運転免許証などの身分証明書を送ってもらっていれば手続を進めることは可能です。
第2 回収することが難しい場合
1 住所が分からない場合
相手方に請求の手紙を出す場合、相手方の住所が必要になりますが、相手方の住所が分からないというケースがあります。
この場合、現在の住所は分からなくても、前の住所だったり、実家などの他の情報が分かる場合は、役所での調査により現住所が判明する場合があります。また、役所での調査では住所が特定できなかった場合であっても、郵便局の転送によりとりあえず前住所に発送することで現住所に転送されて相手方に届くということもあります。
もっとも、転送された場合であっても転送先の情報を郵便局は教えてくれませんので具体的に住所を特定することはできません。
なお、こちらも弁護士会照会であれば特定することは基本的には可能です(DV事案等の恐れがある場合は開示されません。)。
2 相手方が破産準備に入っている場合
大前提として、相手方が破産手続を行っている場合は法的に支払義務が無くなりますので請求自体ができません。
ただ、破産手続は進んでいないけど、破産準備に入っているというケースはあります。この場合はまだ破産していない以上は訴訟等を行うことは可能であり、財産があれば強制執行により回収することも可能です。実際に破産準備中に訴訟手続を行い、給与を差し押さえて回収できたケースもあります。
もっとも、破産準備から実際に破産手続開始の申立てがされた場合は以降は回収できなくなりますので、全額回収に至ることは少ないです。
3 請求金額が少額である場合
こちらは回収することが難しいというよりもメリット・デメリットの問題となります。
例えば、1万円の請求をしたいというご相談をお受けすることがありますが、仮に訴訟や強制執行まで行ってしまうと、貸した金額よりもの多くの費用がかかることが考えられ、この費用は相手方に請求することはできませんので、手続をすればするほど赤字になってしまいます。
この場合、気持ちの部分で許せないから手続をしたいということであれば手続を行うメリットはあるかもしれませんが、経済的には手続を行うことはデメリットでしかありません。
第3 回収できるかどうかは相手方次第という場合
1 相手方に財産が無く勤務先も分からない
法的には訴訟等を行うことは可能であっても、相手方が任意に支払ってくれない場合は強制執行により相手方の財産を差し押さえて強制的に回収するしかありません。逆に言えば、相手方が分割弁済の交渉等に応じてくれる場合は相手方の財産の有無に関係なく回収することができます。
ただ、相手方に財産が無く、勤務先も分からないとなると差し押さえる財産が無いため、結果的に回収できないということも当然あります。
当事務所では相手方が生活保護を受給していても親族等の協力を得て分割支払により回収できたケースもありますので必ずしも回収が不可能という訳ではありませんが、この点は相手方次第であるためやってみないと分からないということになります。
※無関係な親族に支払いを求めることができるわけではありません。あくまで親族の任意の協力が必要です。
2 証拠がまったく無い
訴訟等を行うためには証拠が必要となりますが、実際に会って現金でやり取りを行い、メールなどの記録もまったくないという事があります。このような状況は昔からの知り合いというケースによく見られます。この場合、お金の貸し借り自体は恐らく事実かと思いますので、請求自体は可能です。そうすると、相手方から回答があり、一括または分割で支払ってくれるということでまとまることも多くあります。
しかし、相手方がお金の貸し借りの事実自体を否定されてしまうと訴訟をしようにも証拠がまったく無いため訴訟をしても負けてしまう可能性が十分考えられ、現実的には相手方次第であるためやってみないと分からないということになってしまいます。
以上の次第で、第1については手続を始めること自体が極めて難しいですが、それ以外は回収の見込みがゼロという訳ではありませんので、あとは費用対効果を踏まえてご検討いただくこととなります。